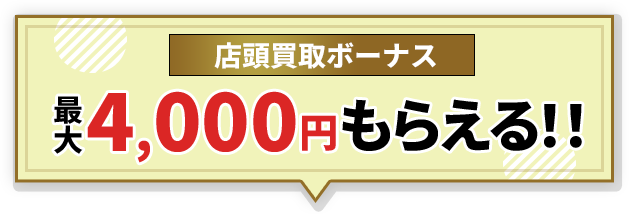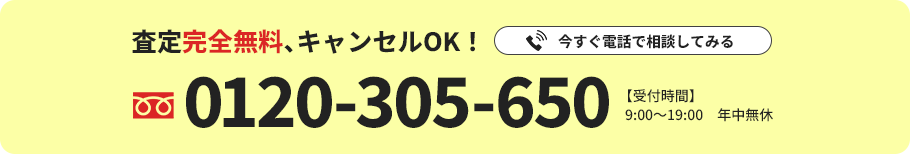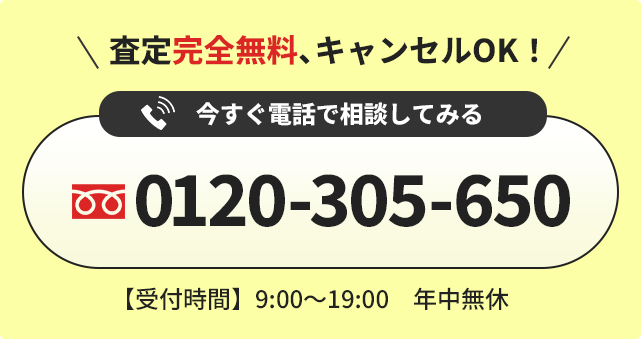ストーブ・石油ファンヒーターの寿命の目安と故障サイン

ストーブや石油ファンヒーターのようなガス・石油機器の寿命は、『一般社団法人 日本ガス石油機器工業会』によると、石油ファンヒーターは8年、ガスファンヒーターは10年が目安とされています。
古いモデルでは製造年月日の記載がない場合もありますが、2000年以降に製造された製品であれば本体の背面や底面に製造年月日が書かれているはずです。
使い続けて年数が経っている場合は、一度確認してみましょう。
寿命前であっても以下の症状が出ている場合は、安全のため買い替えや処分を検討してください。
- エラーコードが何度も表示される
- 電源コードが劣化・断線している
- 炎が安定しない・燃え上がりすぎる
それでは、順番に詳細を説明していきます。
エラーコードが何度も表示される
使用中、頻繁にエラーコードが表示される場合は、内部の部品が劣化している可能性があります。
しかし、フィルターが詰まっているといった原因もありますので、一度フィルター掃除を行い確認してみましょう。
掃除を行ってもエラーコードが多発し、改善しない場合は故障のサインです。
電源コードが劣化・断線している
通電しない、パネルが光らない、スイッチが入らないといった場合は、電源コードが断線しているかもしれません。
断線部分が見える場合は、すぐに使用を中止してください。
ショートして火災につながる恐れがあります。
炎が安定しない・燃え上がりすぎる
炎の大きさが一定でなく、大きすぎる場合は内部故障や灯油供給の不具合が考えられます。
頻繁に発生する場合は使用を続けず、処分や修理または買い替えを検討しましょう。
故障の症状が現れたら買い替え・処分を
上記のような異常がある状態でストーブ・石油ファンヒーターの使用を続けていると
- 発火・爆発
- 不完全燃焼による二酸化炭素中毒
といった重大事故につながります。
2009年以降製造の製品は、製造から10年経過で有料法定検査が義務付けられています。
異常がなくても10年経っていれば、点検するのをおすすめします。
石油ストーブ・石油ファンヒーターの安全な処分方法

ここからは、実際に石油ストーブやファンヒーターを処分する方法を紹介していきます。
主な方法としては
- 自治体の粗大ごみとして処分する
- 家電量販店で引き取ってもらう
- 不用品回収業者を利用する
- リサイクルショップで買い取ってもらう
などの方法が一般的です。
順番にさらに詳しく見ていきます。
ストーブは「小型家電リサイクル法」の対象
壊れて使えないストーブ(電気式・一部の石油ファンヒーターを含む)は「小型家電リサイクル法」の対象品目です。
この法律は、2013年4月1日から施行された「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」で、廃棄物を減らすために制定されました。
使わなくなった小型家電からレアメタルや貴金属を回収して再利用するのが目的で、自治体や回収拠点で適切に回収されます。
対象になるかは自治体や製品の種類で異なり、電気ストーブはほぼ対象、石油ストーブ・石油ファンヒーターは対象外も多いといった違いがあります。
「冷蔵庫・洗濯機(乾燥機)・エアコン・テレビ」の4種の家電が対象となる「家電リサイクル法」とは違い、小型家電リサイクル法は収集運搬料金の徴収はありません。
自治体の粗大ごみとして処分する
最も一般的なのが自治体の粗大ごみ回収です。
手順は以下の通りです。
- 電話やウェブから回収を申し込み、費用を確認する
- 粗大ごみ処理券をスーパーやコンビニで購入
- 必要事項を記入し、対象製品に貼り付ける
- 指定日に指定場所へ搬出する
名古屋市ではストーブが500円、ファンヒーターが1,000円程度で回収可能です。
ただし、回収日まで待つ必要がある、自分で運搬する手間がかかる点については注意が必要です。
重量のあるモデルで「持ち運びは厳しい」という方は、ほかの方法を検討しましょう。
ごみ処理センターへ持ち込む
ストーブ・石油ファンヒーターを車で運べるなら、ご自身で直接持ち込みも可能です。
重量制のため、粗大ごみ回収より安く済む場合もあります。
自治体によっては予約や受付時間が決まっているため事前確認しておくとスムーズです。
家電量販店で引き取ってもらう
家電量販店の多くは、新品購入時に古い製品を引き取ってくれるサービスを行っています。
ただし、ストーブや石油ファンヒーターは冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法の対象ではなく、小型家電リサイクル法の対象となるため、対応していない店舗もあります。
あらかじめ家電量販店に問い合わせするか、購入時に確認するのがおすすめです。
リサイクルショップで買い取ってもらう
製造年が新しく状態の良い製品であれば、買取対象になるかもしれません。
リサイクルショップに買い取ってもらえれば処分費用はかからず、逆に収入が得られるのでとてもお得な方法といえます。
査定額は製造年数や需要に左右されるため、持ち込み前に問い合わせると安心です。
不用品回収業者を利用する
ストーブ・石油ファンヒーター以外にも処分したいものが複数ある時や、少しでも早く回収してもらいたいなら、不用品回収業者が便利です。
こちらが指定した日時に自宅まで回収に来てくれるため、手間もかかりません。
分別や運び出しの手間もなく指示だけで、複数の不用品を同時に処分できる点も魅力です。
費用は自治体での回収と比べると割高に感じるかもしれませんが、買取可能な不用品回収業者を選べば、再利用できるものは買い取って作業費から相殺してもらえます。
結果、思っていたより費用が安くなったというケースも少なくありません。
ただし、液体の処理をはじめ灯油処理に対応していない業者もあるため、事前確認は必須です。
便利な不用品回収業者ですが、中には悪質業者による高額請求や不法投棄のリスクもあるため、評判や実績をしっかりチェックして選びましょう。
ファンヒーターやストーブの買取相場・回収できる品目や費用の相場についてはこちらをご参考ください。
残った灯油の抜き取り手順

本体の中にまだ灯油が残っている場合は、どのように処分すればよいのでしょうか。
灯油が残ったままだと運搬の時にこぼれて危険ですので、粗大ごみとしてストーブやファンヒーターを処分する場合は、必ず給油タンクを空にする必要があります。
安全な灯油の抜き取り手順をご紹介します。
灯油の抜き取り手順
- 電源を切り、コンセントを抜く
感電や誤作動防止のため、必ず先に電源を落とします。 - タンクを本体から取り外す
持ち手を持って静かに取り外します。 - 灯油ポンプを用意する
手動式ポンプまたは電動式ポンプを使用します。
電動の場合は防爆仕様のものがおすすめです。 - 灯油を安全容器に移す
ポリタンクや金属製容器に移し替えます。
ペットボトルは静電気や破損の危険ありますので避けましょう。 - 残量が少なくなったら吸い上げ口を傾ける
タンク内の底に残った灯油も可能な限り抜き取ります。 - 空になったタンクを陰干しして乾燥させる
直射日光を避け、風通しの良い場所で完全に乾燥させます。
残った灯油の正しい処分方法

灯油を安全にストーブから抜き取ったら今度は処分方法を考えなくてはなりません。
以下では残った灯油の量別で、処分方法をご紹介します。
少量の場合
可燃ごみで処分する
新聞紙や布に吸わせて可燃ごみとして廃棄します。
給油ポンプやスポイトで吸い出しペットボトルに移す方法もありますが、自治体によって処理方法が異なるため事前確認が必要です。
大量の場合
ガソリンスタンドに持ち込む
ガソリンスタンドや灯油販売店に相談すると、安全に処理してもらえます。
持ち込む前に対応可能か事前確認しておきましょう。
手数料がかかる場合がありますが、危険物の取り扱いに慣れた業者に任せるのが安心です。
使い切る
使用可能な季節で、安全な状態の製品であれば運転して灯油を使い切る方法もあります。
運転し続けて使い切ってしまえば灯油が残らないので処分も簡単です。
ただし、故障している場合や炎が不安定な場合は危険なので、この方法は避けましょう。
ストーブ・石油ファンヒーターによっては、説明書に空焚きの方法が記載されていますので確認してみるとよいでしょう。
まとめ

今回はストーブや石油ファンヒーターを安全に処分する方法についてご紹介しました。
ストーブや石油ファンヒーターは「火」を扱うため故障したものをそのまま使い続けるのはたいへん危険ですので、寿命や故障サインを見逃さず、今回ご紹介した安全な方法で早めに処分するのがおすすめです。
不要になったストーブやファンヒーターは「買取いちばんドットコム」でも買取可能です。
状態が良ければ、処分費用がかからずに現金化できるかもしれません。
自分では持ち運べないストーブや石油ファンヒーターでも、スタッフが出張回収・査定を行います。
名古屋市内なら30分以内での訪問も可能ですので、急を要する方にもご活用いただけます。
引越し先の部屋が暖かくで使う必要がなくなった、新しいものに買い替えた……といった事情で持て余しているストーブがあれば、ぜひ一度ご相談ください。