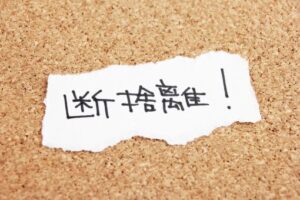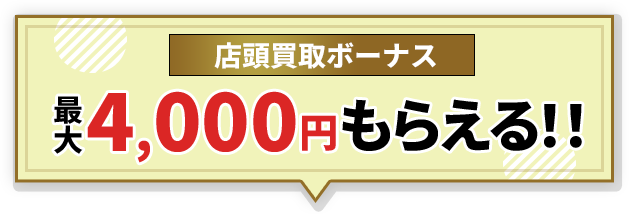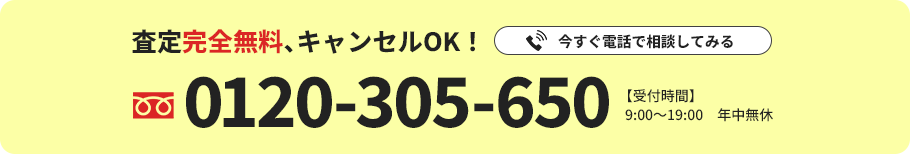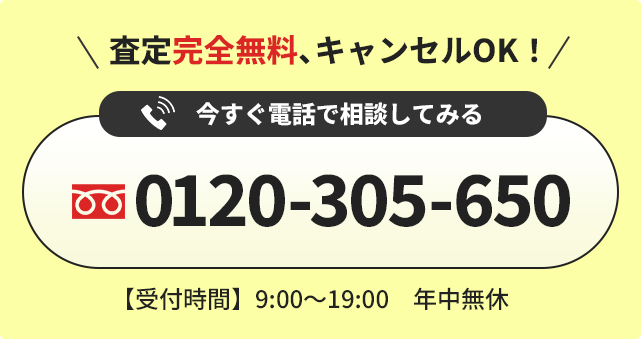物干し竿について

物干し竿のような大きなものを捨てようと思ったとき、どのように捨てたらいいか迷いますよね。
さらに物干し竿は金属でできており、長さもあるので分別方法に迷う方もいるのではないでしょうか。
ここでは物干し竿の素材や何ごみになるかについて、紹介していきます。
物干し竿の素材
物干し竿の素材は主に以下の3つに分けられます。
| 素材の種類 | 特徴 |
|---|---|
| ステンレススチール | サビにくい・耐久性があるなど ただし内部にサビが発生することもある |
| オールステンレス | もっとも丈夫・サビにくい |
| アルミ | 軽量でサビにくい しかし価格が高め |
このように物干し竿は金属製のものが主流で、竿部分に雨水が侵入しないよう端にプラスチックの蓋が付いています。
アルミやスチール、ステンレスでできた物干し竿はとても軽く、どれもサビにくいのが特徴です。
しかし物干し竿はその軽量化を図るために中が空洞となっており、素材がアルミやスチールのタイプは強度が弱いという弱点があります。
そのため、ストッパーがないと風の強い日は動いてしまうことや、布団のように重たいものを干しすぎると湾曲しやすいというのがデメリットです。
またコストを抑えるために鉄にステンレスを巻いている製品もあり、鉄が錆びるとで変形したり強度が低下したりすることも。
負担がかかり続けてしまうと、洗濯物を乾かしている最中に物干し竿が折れてしまうケースもあるので注意が必要です。
物干し竿は何ごみで処分できるの?
アルミ、スチール、ステンレス…と物干し竿の素材だけで見ると不燃ごみとして出せるように思いますが、物干し竿は「長さ」がネックとなりそのまま不燃ごみで捨てられません。
一般的な可燃ごみ、不燃ごみとしてものを捨てる際には、一辺の長さが30㎝を超えないようにして指定の袋に納めないといけません。
最近の物干し竿は昔に比べ伸び縮みさせられるとはいっても、短くても1m以上あります。
伸び縮みできないバーのタイプだと長さが2m近くもあるため、そのまま処分するということであれば物干し竿は粗大ごみに分類されます。
ただし物干し竿を切断し、自治体指定のごみ袋に入れられるサイズにすれば「不燃ごみ」で処分できることもあるでしょう。
物干し竿の処分方法

物干し竿を捨てる方法は「粗大ごみ」が一般的です。
しかし手間をかければ「不燃ごみ」で捨てられる場合もあり、その場合は無料で処分できます。
ここでは物干し竿の処分方法を4選紹介しますので、それぞれの特徴や費用を比較しながら選択してみてください。
処分方法1.粗大ごみに出す
もっとも一般的な方法が「粗大ごみ」の戸別収集を利用する方法です。
多くの自治体では一辺の長さが30㎝、または50㎝以上のものは「粗大ごみ」に分類され、物干し竿も該当します。
粗大ごみで捨てるメリットは「自治体なので安心して利用できること」や「比較的安い金額で処分できること」などです。
一方で、事前予約や手数料納付券の購入をしなければならない点に注意してください。
粗大ごみとして物干し竿を処分する際の流れは以下の通りです。
- 電話またはインターネットで予約する(手数料の確認)
- コンビニやスーパー、郵便局などで手数料納付券を購入する
- 手数料納付券に必要事項を記入し、物干し竿に貼る
- 予約した収集日時の当日朝8時までに、自治体が指定した場所に回収場所に出す
粗大ごみとして物干し竿を出すときも、そのサイズに気を遣わなくてはなりません。大きさは自治体によって差がありますが230cm以下と定められている場合が多いようです。
あまりに長いものは折る、切断するなどといった方法でコンパクトにする必要があります。
以下では一部の自治体で粗大ごみを捨て方、処分手数料を紹介します。
| 自治体名 | 処分手数料・備考 |
|---|---|
| 愛知県名古屋市 | 1本につき250円 |
| 神奈川県横浜市 | 2本まで200円(金属製・突っ張りタイプともに) |
| 大阪府大阪市 | 200円 1.5m以上のものは料金が異なる可能性あり |
このように、物干し竿を自治体で捨てる場合は数百円程度で済むことがほとんどです。
しかし戸別回収は1か月に1回程度となることが多く、申し込みのタイミングによっては回収日がかなり先になってしまうこともあります。
また、平日の朝8時までに回収場所まで自分で運搬しなくてはならないため、忙しくて都合が合わないという方や運搬が難しい方、早く処分したい方は別の手段も検討してみましょう。
処分方法2.自治体のごみ処理施設に持ち込む
車に載せられるサイズにまで物干し竿をコンパクトにできるということであれば、各自治体にあるごみ処理施設へ直接持ち込むという捨て方もあります。
自分で運搬するという手間はかかりますが、ごみ処理施設の営業時間内であればいつでも利用可能で、物干し竿以外のごみも同時に処分できるというメリットもあります。
また、処分手数料は重量制を採用していることが多く、軽量な物干し竿であれば戸別回収よりさらにお得に処分できるかもしれません。
しかしごみ処理施設の数は多くはないため、自宅からの距離や利用手順を事前に確認しておくのがおすすめです。
事前予約が不要な場合もあれば、前日までに予約が必要な自治体もあり、地域ごとのルールが異なる点にも注意しましょう。
ここでは愛知県名古屋市での、自己搬入の手順をご紹介します。
- 「可燃ごみ」と「不燃・粗大ごみ」に分別する
- ごみを車両に載せた状態で、ごみが発生する区の環境事業所で受付する
- 受付後、そのまま指示されたごみ処理施設へ運搬する
- ごみ処理施設でごみを下ろす
- 軽量したごみに対し、10㎏ごとに200円の手数料を現金で支払う
名古屋市では事前予約が不要ですが、受付場所と搬入場所が異なる点に注意が必要です。
また、物干し竿は伸縮できるものがほとんどですが、短い状態でも2mほどとなります。
長いものでは4mほどあり、お持ちの車に載せて運搬できるか確認しておきましょう。
処分方法3.不燃ごみとして処分
指定のごみ袋に入るサイズまで物干し竿を小さく切断できれば、不燃ごみとして処分できます。
その場合かかるのはごみ袋代だけで、処分費用がかかりません。
しかし物干し竿の解体作業には労力や手間がかかります。2m近いものを解体するのでスペースも必要となりますし、パイプカッターという工具も必要です。
物干し竿の解体に必要な道具を紹介します。
- パイプカッター(直径30~32㎜くらいの)もしくは金属用ノコギリ
- 軍手
- メガネやゴーグルなど目を保護するもの
一般的にパイプカッターや金属用ノコギリは、ホームセンターで1,000円ほどで購入できるでしょう。
のこぎりとは違い、カッターの刃と円柱の周囲を回転させながらカットするので強い力は要らず、女性でもお好みのサイズに物干し竿を解体できます。
その際、物干し竿の直径の長さに合ったパイプカッターを購入するようにしましょう。
100円ショップの「ダイソー」でも、100円ではありませんがパイプカッターは売っています。
ただしダイソーのパイプカッターは、製品によってはステンレス製の物干し竿が切れない時もありますので注意が必要です。
袋に入るサイズまで無事に物干し竿の解体ができたら、お住まいの地域のごみカレンダーで不燃ごみの日を確認して、回収場所へ出せば処分完了です。
不燃ごみで物干し竿を処分するときの費用の目安
不燃ごみは「無料」としている自治体が多く、処分費用は指定ごみ袋代のみです。
ただしパイプカッターや金属ノコギリなどの工具を持っていなかった場合、新しく購入する必要があるため数百円~1,000円ほどかかります。
わざわざこのためだけに工具を買うのは気が引けますが、今後もパイプカッターを利用する機会があるのなら買っておいてもいいかもしれません。
処分方法4.販売店舗に物干し竿を引き取ってもらう
処分だけでなく新しく物干し竿を買い換えるということであれば、物干し竿を購入するホームセンターで回収してもらえるケースもあります。
「カインズホーム」や「ビバホーム」では、条件を満たせば無料で古い物干し竿を引き取ってもらえますので、買い替えの予定がある場合は検討してみてください。
以下に物干し竿の引き取りサービスを実施している店舗を紹介します。
| 店舗名 | 利用条件 | 料金 |
|---|---|---|
| カインズ | ・対象商品を1点購入すると、同じ製品・同じ数量を無料で引き取り ・引き取ってもらう古い物干し竿を店舗に持ち込み ・オンラインでの購入の際は納品書または明細書が必要 | 無料 |
| ビバホーム | ・対象商品を1点購入すると、同じ製品・同じ数量を無料で引き取り ・引き取ってもらう古い物干し竿を店舗に持ち込み | 無料 |
処分方法5.金属スクラップ工場に持ち込む
アルミやステンレスなど金属でできている物干し竿は、金属のスクラップ工場へ持ち込み、買い取ってもらえる場合があります。
買取値が付かなかった場合でも無料で引き取ってくれるため、安く処分したい方にはおすすめの方法です。
ただしスクラップ工場へは自分で持ち込まなければならないため、近くに工場がないときは運搬に時間がかかります。
また、どのスクラップ工場でも物干し竿を取り扱っているというわけではないため、事前に問い合わせて確認しておきましょう。
処分方法6.ネットオークションサイトやフリマサイトに出品する
状態のよい物干し竿であれば、メルカリやラクマなどのフリマサイトやヤフーオークションなどを利用して売却することも可能です。
このようなサイトでは個人間でのやり取りになるため、一見売れなさそうなものでも売れる可能性があります。
売却できればお得に処分できるため、とにかく費用を抑えたいという方は検討してみてください。
ただしフリマアプリで売却する際の送料は出品者が負担する場合も多く、物干し竿は送料が高額になりやすいため注意しなければなりません。
さらに梱包や発送手続きなどもこちらで行うため、手間がかかります。
また物干し竿は新品での購入価格が安価のため、一般的な金属製の物干し竿は新品でも買い手がつかないかもしれません。
たとえば大手フリマサイトである「メルカリ」を見てみると、室内用の大きな物干し竿セットや天井からの吊り下げ式物干し竿など、少し高級なものが多く出品されています。
物干し竿を出品しても売れない可能性もあることを知っておきましょう。
処分方法7.不用品回収業者に依頼する
物干し竿をとにかく手間をかけずに処分したい方や、引っ越し・大掃除などで物干し竿以外にも処分したいものが多くあるという場合におすすめしたいのが不用品回収業者です。
不用品回収業者は自宅から出た不用品を分別することなく、そのままの状態で自宅まで回収に来てもらえます。
回収日は自分の都合に合わせて選べるため、土日や夜間でも対応してもらえるというのもメリットの一つでしょう。
物干し竿は自治体で処分する場合、回収日が少ないことや事前予約が必要なこと、自分で回収場所まで運搬しないといけないなど不便な点もあります。
回収日が何週間も先になってしまった場合は、それまで保管しておかなければならないため急いで処分したい方は困ってしまいますよね。
一方、不用品回収業者に依頼すれば電話やメールで簡単に依頼ができ、最短ではその日のうちに処分できます。
さらに物干し竿と一緒に重たい物干し台の処分をしたいというときにも便利な方法です。
ただし物干し竿1本で回収を依頼すると、ほかの処分方法よりもかなり割高になってしまいます。
家庭内でほかに不用品があるときには、トラック1台でいくらというような「定額プラン」や「パックプラン」、不用品の買取サービスを利用するとお得です。
処分方法ごとのそれぞれの違い
ここまでお伝えした、物干し竿を処分する際の日数や費用の違いをわかりやすく一覧にしてみました。
処分方法を選択する際の参考にしてみてください。
| 処分方法 | 処分までの日数 | 処分費用 |
|---|---|---|
| 粗大ごみ(戸別回収) | 7日から30日(月に1回) | 数百円 名古屋市では250円(物干し竿)~500円(物干し台)※手数料納付券の費用 |
| 粗大ごみ(自己搬入) | 1日~2日 | 数百円 名古屋市では10㎏ごとに200円 |
| 不燃ごみ | 1日から30日(月に1~4回) | 無料(自治体によってごみ袋代など) 解体のための道具の費用(1,000円程度) |
| 販売店で引き取り | 1日 | 新しい物干し竿の購入費用 |
| 金属スクラップ工場に持ち込む | 1日 | 無料(買取の場合は収入あり) |
| フリマサイト・ネットオークションの利用 | 1日~(売れない可能性あり) | 売却できれば収入になるが、送料や梱包材を負担する可能性がある |
| 不用品回収業者 | 1日 | 業者によって異なる 3,000円~5,000円程度 |
自治体での処分は回収日が決められているため、捨てるまでの時間がかかりやすいのがデメリットです。
また、利用するためには予約や手続きが必要になることもあり、自分で運搬しなければならないのも負担となるでしょう。
販売店での引き取りや金属スクラップ工場の買取は、買い替えや近くに工場があるなど、条件次第では便利な方法です。
またフリマサイト・ネットオークションは、時間や手間をかけてでもお得に物干し竿を処分したいという方には最適と言えるでしょう。
とは言え物干し竿が売れない可能性があるため注意しなければなりません。
不用品回収業者は「とにかく手間や時間をかけずに物干し竿を処分したい」という方におすすめの方法です。
最短でその日のうちに物干し竿を自宅まで引き取りに来てもらえるうえ、自分で運搬せず処分してもらえます。
ほかにもさまざまな物を回収・処分してもらえるので、不用品が多い場合には検討してみてください。
コンクリートでできた物干し台の捨て方は?

物干し竿を処分する際に大変なのが、支柱を固定するための物干し台の捨て方です。
物干し台にはブロー台と呼ばれる中に水を入れて重石にするものと、コンクリートの土台のものがあります。
コンクリート台は処分料が高めなのと処分ができない市区町村もあります。
以下は物干し台の処分費用の一覧になります。
| 自治体名 | 処分費用・備考 |
|---|---|
| 愛知県名古屋市 | 500円 1個単位 ブロック付は1ヶ月に2個まで |
| 神奈川県横浜市 | 1,000円 コンクリート製の台座のもの ・台座についている支柱は、台座1つに対して1本までは1式として申込可(ただし、台座に通常2本さして使用するものは、2本まで1式として申込可) |
| 大阪府大阪市 | 700円(重り付) 200円(重りなし) |
コンクリート台は安定感もあり長持ちしますが、適正処理困難物に指定する自治体もあるため注意しなければなりません。
適正処理困難物となっている自治体では一般のごみでは収集してもらえず、廃棄物処理業者や不用品回収業者に依頼して処分します。
物干し竿の処分でよくある質問

物干し竿を処分する際によくいただく質問をご紹介します。
Q.一番早く、手間なく処分する方法はありますか?
A.不用品回収業者を利用する方法がおすすめです
不用品回収業者なら土日や夜間など、都合に合わせて利用でき、業者によっては即日対応が可能です。
手数料納付券も購入や手続きなども必要なく、梱包や運び出しなどの労力や手間もかかりません。
Q.物干し台もまとめて処分できますか?
A.基本的には可能です。しかし自治体によってはコンクリートの処分ができない場合もあります
名古屋市の場合は物干し台は500円で粗大ごみとして処分できますが、自治体によっては物干し台の材質であるコンクリートを適正処理困難物に指定しており、回収してもらえないこともあります。
お住まいの自治体でコンクリートが適正処理困難物に指定されている場合は、廃棄物処理業者や不用品回収業者に自分で処分の手配をしなければなりません。
Q.不用品回収業者はどこで探せばいいでしょうか?
A.当ホームページからもお問い合わせが可能です!
お住まいの地域と不用品回収業者、で検索すれば不用品回収業者がたくさん出てくると思いますが、自分に合った業者を見極めるのは大変です。
そのため業者のサイトをいくつか比較し、2~3社程度で見積もりを取るのがおすすめです。
当社「買取いちばんドットコム」では、電話では専用オペレーターが対応するほか、メールやLINEからでも査定、ご相談が可能です。
ご相談は無料ですし、他社様とも相見積もりをしていただいてもOKですので、ぜひ一度お問い合わせください!
まとめ

今回の記事では、物干し竿の捨て方をご紹介しました。
物干し竿は自治体の「粗大ごみ」で処分する方が一般的です。
処分費用が安く確実に処分できる方法ではありますが、処分手続きや運び出しの手間がかかります。
また物干し竿は長く、重さもある程度あるため運搬が面倒に思う方も多いかもしれません。
簡単に処分したいというときは、不用品回収業者の利用を検討してみましょう。
不用品回収業者は物干し竿以外の不用品も回収しており、コンクリート台座のような自治体では処分しにくいこともあるものや、重たいものも簡単に処分してもらえます。
家の整理や引っ越しのときなど、不用品がたくさん出るときにはぜひ検討してみてください。