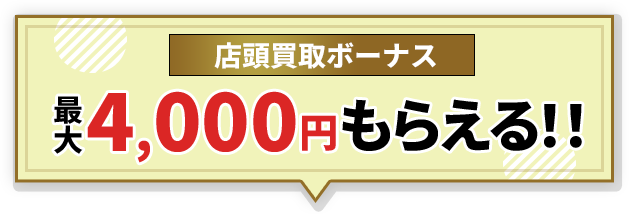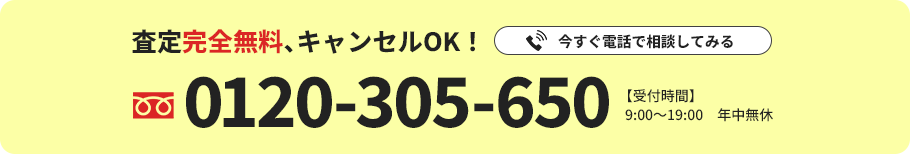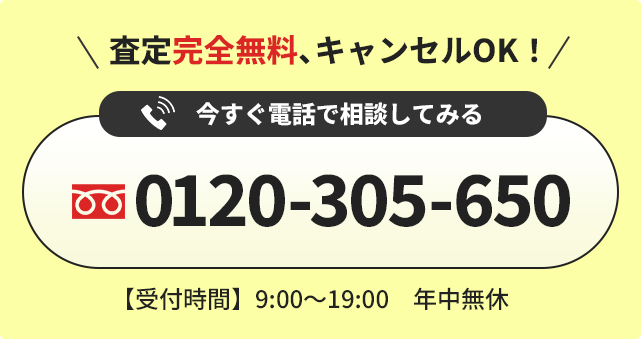一人暮らしの大掃除はコレが大事!大掃除を成功させるコツ

一人暮らしの方が大掃除を始める場合、大変なのは次のようなことです。
- 時間がなかなか取れない
- 一人ですべてやらないといけない
- モチベーションが上がらない
一人暮らしであるため、ほとんどの方は自分だけで掃除を進めることになるでしょう。
そのため、家の中の掃除を進めながら料理や洗濯など通常の生活で必要なこともやらなくてはならず、時間的にも体力的にも大変だと思う人も多いかもしれません。
また、学生や新社会人の方は「忙しくてそんなに時間が取れないよ」と思うこともあるでしょう。
さらに一人暮らしということもあり、「自分以外に家の中を見る人がいない」「キレイにする目的が見当たらない」など、掃除をするモチベーションが上がらないこともありますよね。忙しくて体力的にも余裕がなければ尚更です。
そこで一人暮らしの大掃除はコツを抑え、頑張りすぎずに進めることが大切になってきます。
大掃除のコツ1.完璧を求めすぎない
一人暮らしの大掃除をしていくうえで大切なのは「完璧を求めすぎないこと」です。
掃除を進めていくと「せっかく大掃除をしたのだから……」と、家の中すべてをキレイにしようと思われる方も多いですが、実際に一人であちこち掃除をこなしていくのは容易ではありません。
また掃除をしていくうちに「あそこも」と、つい目が向いて掃除の範囲を広げてしまうかもしれませんが、そうしていくうちに時間と労力を消費し、途中でやめたくなってしまうことも。
一人暮らしの大掃除は「普段できない場所」に限定するとスムーズに掃除が進みます。
また家全体のうち、8割程度できたらOKと目標を低めに設定して、頑張りすぎないこともポイントです。
大掃除のコツ2.大掃除の計画を立てる
大掃除をしよう!と思い立ったら、掃除の計画やスケジュールを立てることも大切です。
やみくもに掃除を進めてしまうと1日にどこまでやればいいのかわからず、疲れてしまったり中途半端になったりして最後まで掃除ができなくなることもあるでしょう。
大掃除の計画を立てる際に次のことを決めるのがポイントです。
- どこの箇所を掃除するか
- 掃除に使える時間はどれだけあるか
大まかに、これだけ決めておくだけで大掃除の進み具合がグッと変わります。
例えば、「キッチン、お風呂、リビングだけ掃除する」「期間は2日のみ」などを決めておくと、掃除のイメージが付きやすいですよね。
さらに1日目はキッチン・お風呂だけ、2日目はリビングのみというように、細かく計画を立てれば動きやすくなります。
もちろん、時間に余裕がある方やもっと掃除箇所を増やしたいということであれば、自分の予定に合わせて日数を増やしていきます。
ただし年末は何かと忙しい時期でもあるため、余裕を持って早めに計画するのがおすすめです。
大掃除のコツ3.必要な掃除道具を揃えておく
大掃除をすると決めたものの、初めての一人暮らしで今までまともに掃除をしたことがない……という人もいるかもしれません。
大掃除のときには普段やっていない場所の掃除や作業をすることも多いため、掃除道具もそれに適したものを用意したほうがよいでしょう。
あると便利な掃除道具は次のようなものです。
- 雑巾
- バケツ
- ゴム手袋
- マスク
- 紐(ごみをまとめる用に)
- 大きなごみ袋(自治体指定のもの)
- 専用洗剤(食器用・カビ用・油汚れ用など)
- ブラシ(小さなものは歯ブラシでももOK)
- メラミンスポンジ
洗剤は重曹やクエン酸、オキシクリーンや、住居用洗剤など、さまざまな種類が売られていますので、掃除したい場所や用途に合わせて購入しておくとよいでしょう。
ただし成分によって取り扱いに注意が必要なものもありますので、パッケージにある注意書きを読むようにしてください。
【抑えておきたい】一人暮らしの大掃除でやっておきたい場所

大掃除のコツはわかったけど「じゃあ実際にどこを掃除すればいいの?」と思われる方もいるかもしれませんね。
ここでは一人暮らしの大掃除でここはやっておいたほうがよい、という場所を紹介します。
すべてをやれない場合は、特に汚れている場所を選んで掃除しましょう。
1.冷蔵庫の中
冷蔵庫の中は普段なかなか掃除することもないため、大掃除でやっておきたい場所のひとつです。
年末のように寒い時期に冷蔵庫の掃除をすれば、中に保存していた調味料や食品を一時的に冷蔵庫の外に出しても傷みにくいのでおすすめです。
まずは用意したい道具を紹介します。
- 布巾やウエットシート
- アルコールスプレー
- 食器用洗剤(キュキュットなど)
- ごみ袋
- ゴム手袋
冷蔵庫の中は食品を置くため、使用する洗剤は食器用の「中性洗剤」や「アルコールスプレー」などがおすすめです。
ほかにも自然由来の掃除アイテムである「重曹」を水で薄めたものでもOK。
これらは汚れをキレイに落としつつ、安全性の高い洗剤なので冷蔵庫だけでなくキッチンや子ども部屋の掃除にも向いています。
では早速手順をみていきましょう。
- 調味料や食材など冷蔵庫の中のものをすべて取り出す
- 期限切れのものや傷んでいるものがあれば処分する
- 布巾やウェットシートに中性洗剤を1〜2滴ほど垂らし、冷蔵庫の中を拭き掃除する
- 菌を繁殖しにくくするため、除菌ができるアルコールスプレーで拭く
- ポケットや棚、野菜室、製氷タンクなどは取り外して水洗いをする
- 洗剤を取るために冷蔵庫内部を水拭きする
- 洗った棚や製氷タンク、残った調味料や食材を元に戻す
- 冷蔵庫の表面を拭く
冷蔵庫内には食品のカスやこぼれた調味料・飲料などがあり、意外にベタついたり臭ったりするものです。
頑固な汚れは重曹スプレーや中性洗剤を使って、よく拭くようにしてください。
中性洗剤は1~2滴ずつ雑巾に使用、重曹スプレーは水100mlに対して重曹小さじ1を加え、よく混ぜたら完成です。
余裕があれば扉や引き出しのパッキンも拭いておきましょう。
2.キッチン(コンロ・換気扇)
冷蔵庫の次はそのままキッチンの掃除をしましょう。
キッチンは普段、自炊をしていないという方はあまり入念に掃除する必要はありません。
しかしコンロを使用した料理を作っている場合は、大掃除をするのがおすすめです。
用意したい道具は次のとおりです。
- 布巾やウエットシート
- 油汚れ用洗剤(マジックリン・重曹スプレーなど)
- 食器用スポンジ・メラミンスポンジ
- ゴム手袋
コンロや換気扇の汚れは「油汚れ」が中心です。
そのため油を分解してくれる成分の入ったアルカリ性洗剤を使用するのがポイント。「マジックリン」のように油汚れ専用の洗剤もありますが、「重曹」も油汚れに効果があります。
重曹は冷蔵庫内と同様に「重曹スプレー」にして利用したり、汚れのひどい箇所にはペーストにして塗ったりと色々な使い方ができます。
コンロの掃除の手順は以下の通りです。
- 五徳やバーナーキャップ、魚焼きグリルなど外せるものはすべて外す
- シンクにお湯を溜めて、外したパーツを付け置きする
- 汚れが柔らかくなったところで、重曹スプレーや洗剤をかける
- パーツは食器用スポンジ、メラミンスポンジなどで汚れを取り除く
- コンロまわりやコンロ横の壁、レンジフード、調理台なども洗剤をスプレーし、布巾やウェットシートで拭く
- 乾かしたパーツを元に戻して完了
換気扇は種類によって多少掃除の手順が異なります。
一般的にアパートなど賃貸地住宅に多い換気扇の掃除の手順を以下に紹介します。
- カバーとファンを取り外す
- コンロのパーツと同様に、シンクにお湯を溜めて、外したパーツを付け置きする
- 洗剤を使って、カバー・ファンの油汚れを落とす
- パーツを乾いた布巾で拭き取るか乾燥させてから元に戻す
基本的に油汚れは洗剤を使用すれば落とせますが、どうしても落とせないときはメラミンスポンジを使用すると落とせる場合もあります。
ただしメラミンスポンジは表面を研磨してしまうため、素材によっては傷が残ってしまいます。
使用の際はコンロや換気扇パーツの素材に注意しましょう。
3.浴室
浴室は少し掃除を怠ってしまうと水垢や黒カビが発生し、浴室全体に汚れが広がってしまいます。
特に床や排水溝、壁、鏡や蛇口まわりなどに汚れが付着するため、重点的に掃除しましょう。
用意する道具は次のとおりです。
- 塩素系カビ落としスプレー
- 浴室用中性洗剤
- クエン酸スプレー
- マスク
- ゴム手袋
- ブラシ・スポンジ
カビは一般的な浴槽用の洗剤では落としにくいため、カビ専用の塩素系洗剤を使うのがおすすめです。
ただし塩素系洗剤は刺激が強いため、肌や目などに触れると危険です。掃除の際はゴム手袋やマスクを着用し、換気をしながら作業するようにしましょう。
掃除の手順は以下の通りです。
【カビの落とし方】
黒い汚れはカビの可能性が高いため、カビ専用の洗剤を使用します。
- カビにカビ専用洗剤をかけて数分置いておく
- 汚れがひどい場合はジェル状のものを使用したり、ティシュに洗剤を染み込ませて付けたりして、より浸透しやすいようにする
- 時間を置いた後、シャワーの水でしっかり洗い流す
【床のピンク汚れの落とし方】
床がピンクっぽく変色している原因は「ロドトルラ」という酵母菌の一種で、カビとは別物です。このピンクの汚れは「浴室用の中性洗剤」で落とせます。
- 汚れている場所に浴室用の中性洗剤を振りかけて数分放置する
- 時間を置いた後、ブラシでこする
- シャワーの水でしっかり洗い流す
【蛇口・鏡などの汚れの落とし方】
蛇口や鏡のザラザラは水道水に含まれるカルキやカルシウムが原因のウロコ状水垢です。
水垢はクエン酸スプレーで落とせますが、頑固な汚れは研磨シートやメラミンスポンジなども使ってみましょう。
ただし研磨シートやメラミンスポンジは傷が付きやすいため、目立たないところで試してから使うのがおすすめです。クエン酸スプレーは、水200mlにクエン酸小さじ1杯を加えよく混ぜたら完成です。
- 鏡や蛇口の水垢がある部分を濡らす
- クエン酸スプレーを吹きかけ、その上からラップやキッチンペーパーで覆う
- 1時間ほど放置
- シャワーの水でしっかり洗い流す
4.トイレ
トイレも浴室と同様に水垢汚れが溜まりやすい場所です。
尿ハネや便器内のこびりつきなど、使っていくうちにさまざまな汚れが蓄積されていますので、大掃除の際は入念に掃除しましょう。
トイレ掃除で使用する洗剤は、汚れの種類によって洗剤を使い分けます。
- 普段使用するもの…中性洗剤
- 黒ずみ…塩素系漂白剤
- 黄ばみ・尿石…酸性洗剤
洗剤以外に用意する道具は次のとおりです。
- ゴム手袋
- トイレ用の掃除ブラシ
- トイレ用の流せる掃除シート
掃除の手順は次の通りです。
- 便器の中にトイレ用の洗剤をかけてブラシで磨き、水を流す
- 便座やタンクまわり、床や壁、ドアノブやペーパーホルダーなどは掃除シートで拭く
- ウォシュレットのノズルを引き出し、掃除シートで拭く
- スリッパや便座カバーなどがあれば洗濯する
ウォシュレットのノズルは「ノズル掃除ボタン」や「ノズルおそうじ入/切」などのボタンを押すか、手で引き出します。ノズルは「水垢」や「跳ね返りの便」などが付きやすいため、定期的に掃除するのがおすすめです。
5.玄関・靴箱
玄関も普段掃除できていないという方が多く、大掃除でスッキリさせるチャンスです。
靴箱の中も見直して、あまり履いていない靴があれば処分しましょう。
用意する道具は次のとおりです。
- ほうき・ちり取り
- 掃除機
- ごみ袋
- 雑巾
- 中性洗剤(ウタマロクリーナー・クイックルホームリセットなど)
掃除の手順は次の通りです。
- 靴箱の中の靴をすべて出して、いらない靴があれば処分する
- 靴箱の中をほうきで掃き、砂やホコリを取り除く
- 靴箱内を濡らした雑巾で拭き、扉を開けて乾燥させる
- 靴を靴箱に戻し、玄関タイルの上に物があれば片付ける
- タイルはほうきや掃除機で砂やホコリを取り除く
- 濡らしたブラシやスポンジで水拭きをする
- ひどい汚れがあれば洗剤をかけて拭く
玄関のタイルは素材によって扱いが異なりますが、一般的によく使用される人工素材のタイルはブラシで強く擦ったり洗剤を使用したりしても問題ありません。
中性洗剤以外に重曹・セスキ炭酸ソーダなども使用できます。
6.窓・サッシ
窓ガラスは内側なら手垢やホコリ、油汚れなど、外側は排気ガスや雨、花粉や砂、泥、黄砂などによる汚れが付着しています。
内側・外側共に汚れが付着していると曇ってしまい、窓の外の景色が見えにくくなるほか、家の中も何となくスッキリしない印象になってしまいます。
また汚れを取らずに放置していると取りにくくなってしまうため、定期的に掃除するのがおすすめです。
用意したい道具は以下の通りです。
- 雑巾2枚
- ゴム手袋
- 窓用洗剤(重曹やセスキ炭酸ソーダ、クエン酸スプレーでも可)
- 窓拭きワイパー
- ブラシ(サッシ用)
- キッチンペーパー(サッシ用)
窓掃除は基本的に水拭きで大丈夫です。しかし手垢や油汚れをスッキリ落したいなら洗剤を使用してみましょう。
用途別のおすすめの洗剤は次の通りです。
- 手垢・油汚れ…重曹・セスキ炭酸ソーダ
- 曇り・水垢…クエン酸
セスキ炭酸ソーダスプレーは、水200mlに対してセスキ炭酸ソーダを小さじ1杯入れてよく混ぜ合わせます。
窓掃除の手順は以下の通りです。
- 窓に適した洗剤を吹きかける
- 固く絞った雑巾で水拭きをして、汚れと洗剤を拭き取る
(窓拭きワイパーで水気を取ると便利です) - 乾いた雑巾で乾拭きをする
サッシは以下の手順で掃除します。
- 掃除機や使い古しの歯ブラシなどを使って、サッシにあるほこりや砂を取り除く
- 雑巾やキッチンペーパーなどで水拭きする
掃除する順番は、網戸→窓ガラス→サッシ・レールで進めると汚れの再付着を防げます。
ほかにもこんな場所の掃除もやってみよう

時間や体力に余裕があれば、ほかの場所も掃除してみましょう。
特に汚れが目立つ場所や片付けたい場所を選んで掃除するのがおすすめです。
1.クローゼット
クローゼットはついつい不要なものが溜まりやすい場所です。
物が多いと使いにくいだけでなく、湿気も溜まりやすくなってしまうためカビが生えてしまい、衣類やバッグなどが傷んでしまう可能性もあります。
大掃除のときにはいらない衣類やバッグ、小物などを見直して処分しましょう。
クローゼット内の物が減ったら棚や床などを水拭きして、扉を開けて乾燥させます。
また普段から布団や冬用コート・ニットなどをしまっている場合、ダニや虫食いの被害に遭うこともあるため、定期的に掃除や換気をするとよいでしょう。
2.照明器具
照明器具はホコリが付着しやすく、キッチンの近くに置いてある場合は油汚れと混ざって簡単に取れにくくなります。
見た目にも健康的にもホコリが付いたままというのはよくないため、大掃除のときにまとめてキレイにするのがおすすめです。
照明器具はホコリだけなら水拭きだけでも大丈夫です。油汚れが付着している場合はアルカリ性洗剤を吹きかけながら優しく取り除きましょう。
3.ベランダ
ベランダは雨風や落ち葉、排気ガスや砂などの汚れが蓄積しやすい場所です。
汚れが蓄積すると排水口の詰まりやカビの発生の原因にもなるため、定期的に掃除しましょう。
ベランダにごみや物を置いているという場合はまず、それらを処分したり整理したりすることから始めます。
物が無くなった後はほうきやブラシを使って落ち葉や砂などのごみを取り除き、住宅用洗剤や重曹スプレーを使いながらブラシで汚れをこすり取ります。その後水で洗い流したら完了です。
このとき、アパートやマンションなどで大量に水が流せないというときはジョウロで少しずつ水を流してください。また手すりや物干し竿も一緒に拭いておくことを忘れないようにしましょう。
一人暮らしの大掃除の負担を軽くする方法

一人暮らしの大掃除は時間と体力を消費するため、途中で嫌になってしまう人もいるかもしれませんね。
ここでは大掃除の負担を軽くするために普段できることを紹介します。
1.普段からこまめに掃除しておく
普段あまり掃除しない人ほど大掃除が大変になってしまいます。どんな汚れも蓄積すると取りにくくなるうえ、作業に時間がかかることで「やっているのになかなかキレイにならない」と、モチベーションが上がらないこともあるでしょう。
できるだけ普段から少しずつ掃除するように心掛けるのが大切です。
例えば「フロアワイパー」や「ハンディモップ」など、手軽に使いやすい掃除道具を目に付くところに置いておき、毎日気付いたら掃除するというのもひとつの方法です。
また1日10分でもよいので掃除する時間を決めておき、ルーティン化するのもよいでしょう。
2.カビ予防や汚れ防止グッズの活用
汚れが付着しないよう予防しておくことも掃除をラクにするコツです。
あらかじめ汚れを溜めにくいように工夫しておくことを「予防掃除」と言いますが、実際に行うポイントは次の通りです。
- 物を減らしておく
- 直接汚れが付かないようカバーする
- 汚れ防止グッズ(洗剤)を使用
掃除しやすくするためには物を減らすことが大切。例えば机や床の上に物を置きすぎず、気付いたときにサッと拭けるようにしておくといつもキレイな状態を保てます。
また、ラグやコーヒーテーブル、間接照明など余計なインテリアが多いとその分お手入れも大変になります。
本当に必要なものだけを家に置くようにしましょう。
汚れが直接付かないよう工夫するのもおすすめです。
換気扇にはフィルター、キッチンまわりの壁はラップを張り付けるなど、汚れが直接付かないようにしておくと取り換えるだけでキレイになります。
ほかにも浴室は「おふろの防カビくん煙剤」を使用したり、ドア下パッキンに「汚れ防止テープ」を貼ったりするのもおすすめ。カビや汚れが付くのを防いでくれるため、掃除の回数を減らせるでしょう。
3.ハウスクリーニング業者を使うのも有効
どうしても大掃除の時間が取れない……というときにはハウスクリーニングやクリーニング業者に頼るのも検討してみてください。
業者では専用洗剤を使用するため自分では取れにくい汚れもあっという間にキレイに仕上げてくれます。
また、業者によってはエアコンクリーニングや不用品の処分などオプションサービスが充実していることも。すべてを業者に任せるのではなく「水回りだけ」や「浴室・トイレのみ」など、要望に合わせてプランを選択できるため上手に利用しましょう。
まとめ

今回は一人暮らしのお部屋の大掃除のコツ、注意点などを紹介しました。
一人での生活とは言え、浴室やトイレ、キッチンなどは汚れが付きやすく、普段からこまめに掃除しておくのが大掃除の負担を減らすコツです。
また、用途に合わせて洗剤や道具を用意し、いつでもサッと掃除できるようにしておきましょう。
大掃除で出た不用品をお得に処分したい方は「買取いちばん」の無料査定をぜひご利用ください。
不用品の処分は大きさや品目によって有料となるため、売って処分できれば費用がかかりません。
「買取いちばん」では大掃除や断捨離時などの大量の不用品や大きなものも、出張買取で手間をかけずに処分できます。
査定後のキャンセルは無料ですのでお気軽にお試しください。
▼こちらの記事もおすすめです